課題を発見するためのWeb分析視点と手法@デジタル神無月
2016年10月19日(水)~20日(木)に、九州最大級のデジタルカンファレンスイベント『デジタル神無月』が福岡にて開催されました。
デジタルマーケティングに関わる第一線のプレイヤー・ツールベンダーが集い、Webや記事には出てこない生の声でのナレッジ共有やディスカッションを行った本イベントは、2日間でのべ600名以上の方が来場されたそうです。
本イベントの2日目『アクセス解析パート』にて、弊社代表土谷が、アクセス解析の第一人者である小川卓さんと共に登壇しました!

コンテンツ
アクセス解析パート概要
30分でECサイトを即興分析!プロのリアルな分析ポイントと手法を大公開
『プロの解析士がどういう視点で、どういった手順で数字を見て、何を考え、何を導き出すのか?アウトプットされる結果だけでなく、その過程を知り、自社もしくはクライアントの課題発見に生かすことができます。』との説明があった本セッション。
書籍では学べない「分析の切り口」や「仮説の立案」について、プロの手法が見られる貴重な機会なため、他セッション以上に熱心にメモを取っている方の姿が目立ったのが印象的でした。皆さん、アクセス解析への関心が高いですね!
ちなみに今回のイベントの流れはこんな感じでした。
- 対象サイトは実在する印鑑のECサイト
- 分析に使用するのはWebサイトとGoogleアナリティクスのデータ
- 分析のお題は「広告比率を下げるための施策を見出すこと」
- 各15分の持ち時間の中で実際にアクセス解析を実施。事前準備無しのぶっつけ本番!
- その後アクセス解析のポイントについてディスカッション
小川卓さんの解析手法
①GoogleアナリティクスでWebサイト概要を確認する
具体的には以下の3点を確認されていました。ざっくりと現状把握されるイメージですね。
- デバイス別にどちらがセッション数・CVRが高いか
- チャネル別に、各流入経路の現状
- 新規とリピートから、初回訪問での購入・複数回訪問での購入どちらが多いか
新規とリピートから、今すぐ客・長期検討する人のどちらがメインかというサイト特性を見ているのが印象的でした。
②ユーザー目線でWebサイトを実際に使ってみて、気になる点をメモする
Webサイトを見ながら、どのコンテンツが有用か、あるいは不要なのかのアタリをつけていて、Webサイトの各コンテンツを見ることでCVRは上がるのか?を分析観点として重視されていると感じました。
③サイトのURL構造を把握する
特定のカテゴリページに共通で含まれる文字列をメモしておいて、後にアドバンスセグメントでグルーピングする際のルールを確認されていました。
この作業は弊社でも行いますが非常に重要です。事前にまとめておくかどうかで分析効率や、分析出来る事が大きく変わってきます。
④メモした分析観点を、アドバンスセグメントを使用しグルーピングし分析する
各コンテンツ経由でCVRが上がるのかどうかを、アドバンスセグメントのシーケンス機能を活用し確認されていました。
例えば「TOPページ->商品一覧->商品詳細」へ遷移した場合と「TOPページ->商品詳細」へ遷移した場合、という風にデータを切り分けて比較されていました。
また、「イベント検知が出来ればより楽なんだけど」とおっしゃっていて、効果測定の事前設計はやはり重要だなぁと感じました。取りたいデータがあるけど設定されてなくて計測できないWebサイト、よくあるんです。。。
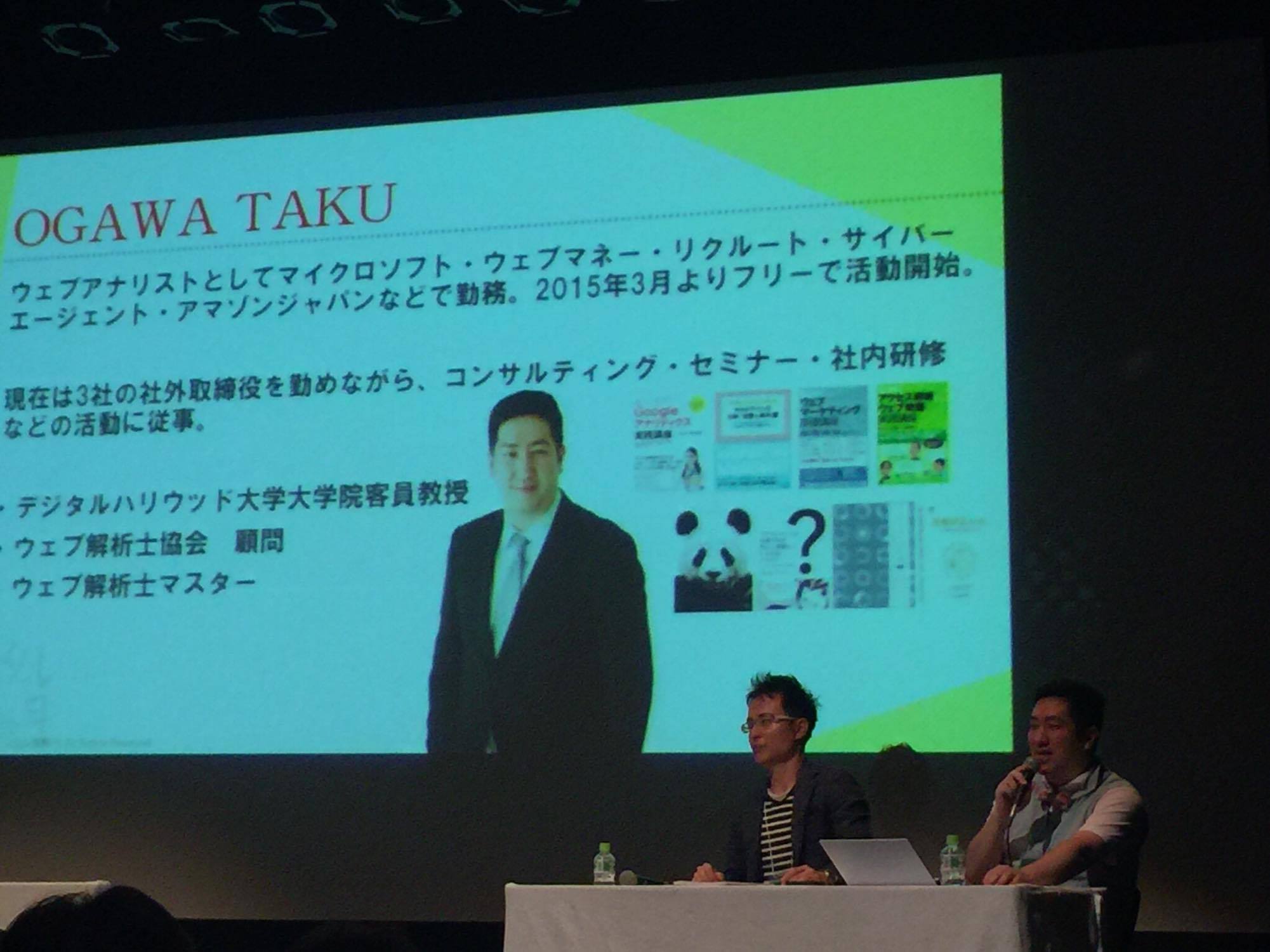
小川さんの分析は、数字を元にユーザーをセグメントし、行動パターン毎に分析を進めるスタイルでした。全体を通じて、ポイントはCVRの上がる行動・下がる行動データから見つけることと感じました。
土谷の解析手法
①GoogleアナリティクスでWebサイト概要を確認する
こちらは小川さんと同様、まずはGoogleアナリティクスの数値から大まかに現状把握をする流れは一緒です。
②改善の方向性について仮説を立てる
お題のECサイトのCVRが十分高いサイトであることに着目し、大きくCVRを上げる改善は難しいのではないか?という仮説を立てていました。
そこから、分析のセオリーとしてまずは、購入に近いポイントから課題がないか確認するという観点から、GAの「コンバージョン」項目を確認していました。
③競合はどこか、競合と比べてどう見えるかをユーザー目線で確認する
ターゲットとなる個人客・法人客それぞれの目線で、競合サイトと比較して使いやすいサイトであるかどうかを確認しました。
今回は競合サイトと非常に作りが似通っていて差別化がされていない、という特徴がありました。
④商品特性からユーザーの検討フローを想像する
印鑑はコモディティ化している商品という商品特性から、どうすればユーザーに選ばれるかを考えていました。
検討期間は短い商材であり、商品の予備知識もユーザー側にはあまり無いことから、サイト上の商品点数がかなり多く選びづらいのではないか?という仮説を立案。
そもそも商品点数がこんなに必要なのか?売れている商品を目立たせることで売上を伸ばせるのでは?という改善案を立てていきました。
売れてる物をもっと売るか、売れないものをもっと売るか。という判断をどう踏まえるか?という話まで盛り上げたい
— みんみん@平和主義 (@honmono_minmin)
2016年10月20日
こんな観点でツイートしてくれている方がいました。
弊社としては、「上手く行っているものを伸ばす」というビジネス上のセオリーを持っています。
ビジネスは確率です。
そこで、売れないものをがんばって伸ばすより、既に売れている商品をさらに伸ばす方がビジネス的には確率が高いため、売れている商品を伸ばす方向でまずは考えていきます。
⑤具体的に伸ばせそうな商品はあるか確認する
アドバンスフィルタで商品をフィルタリングし、売上に占める比率を見て仮説の検証を行いました。実際に、売れ筋の2種類の商品が売上の5~6割を占めていたため、売れている商品を目立たせるという改善案の根拠となりそうでした。
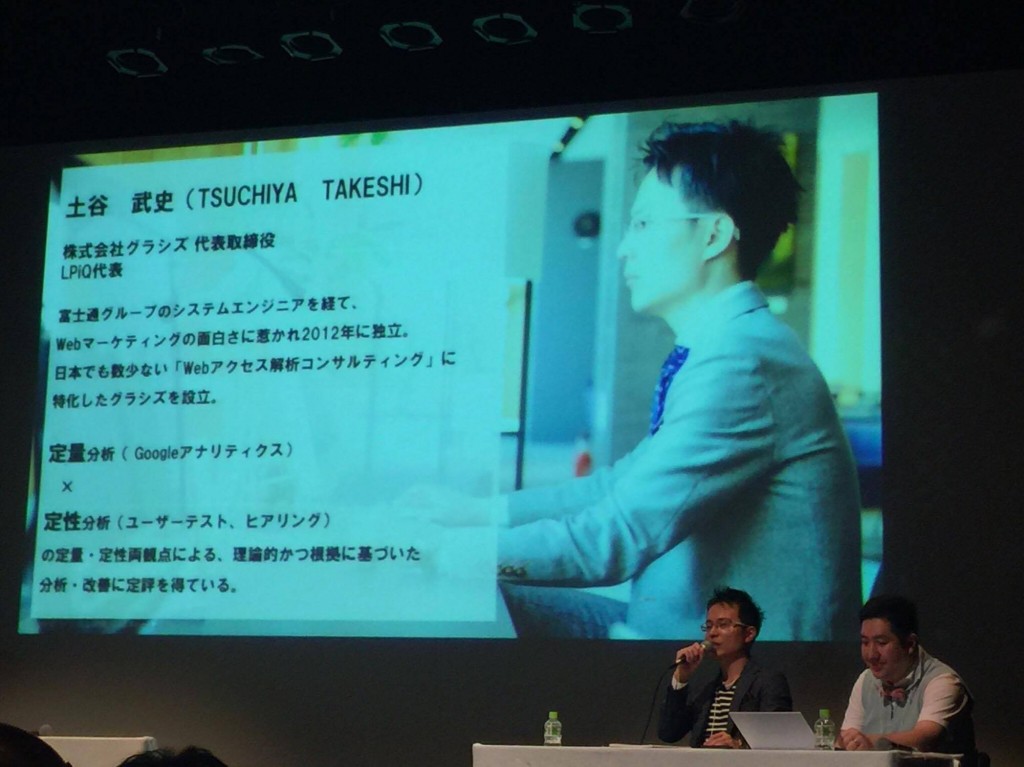
土谷の場合は数値的事実から、改善インパクトの大きい箇所はどこか?という観点から、商品特性や競合比較をしながら、仮説と具体的な改善案を考えつつ分析を進めていくことが特徴的かと思いました。
アクセス解析を行う際のポイント
両者とも共通していたのは「最初はGoogleアナリティクスのデータをあまり見ないこと」と「競合のサイトを確認すること」
小川さんがおっしゃっていたように「ずっとデータを眺めていることほど無駄なことは無い」です。ユーザー、集客、行動、コンバージョン全てのレポートに細かく目を通すよりも、概要を確認したらWebサイトを見て、分析観点のアタリを付けに行くのが大事ですね。
競合サイトの確認理由は異なっていたものの、ユーザー目線で比較検討してみることが大切という点は共通していました。
- 小川さん「CVRをクリエイティブ改修で上げる際に他社の取り組みを見る」
- 土谷「ユーザー目線で、他サイトと比べ自社サイトは魅力的かどうか、差別化ポイントを確認するために見る」
最後に、それぞれ大切にしているアクセス解析のポイントを以下のように話されていました。
- 小川さん「離脱が発生しているバケツの穴は塞ぎながら、ユーザーの心や気持ちを動かさなければならない」
- 土谷「今やるべきことと、やらなくて良いことを見極める。そして、最も改善インパクトが見込める投資の力点を見極める」
ユーザー目線と、分析観点を持つこと。どちらも数値ばかり見ていると忘れがちになるので、今一度意識し直しました。
まとめ
2人とも「15分は短い」と言われていて、恐らく会場で聞いていた大多数の方も同じように感じたのではないでしょうか。限られた時間の中で、次々と改善に繋がりそうなポイントを抽出していく姿は、ある種魔法のように面白く感じたかもしれません。
ですが、大切なのは分析することだけではなく、分析結果を元に改善を行い続けることです。
アクセス解析を行うことに満足せず、改善アクションを行い続ける覚悟を持つことが大切だと再認識できたセッションでした。
アクセス解析で成果を出したい!という方は以下の記事もご覧ください。
結果が出るクライアント8箇条、出ないクライアント6箇条

